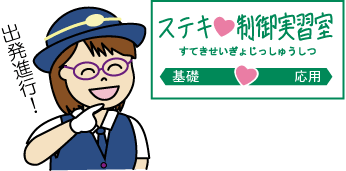 |
|
|||
| みなさんこんにちは。見習い講師の里枝です。今回は、鉄道模型の信号機のいよいよ本格的にしちゃいます。 単純な閉塞区間での信号動作+タイマー復帰という前回の仕様で回路もそのままにPCBEを使ってパターンを起こし、例によって「趣味の基板屋さん」にて専用基板の製作をお願いしました。 さらなる小型化と汎用化に成功しましたので、鉄道模型で自動信号制御を検討されている方々にもお試し頂ける内容だと思います。 |
||||
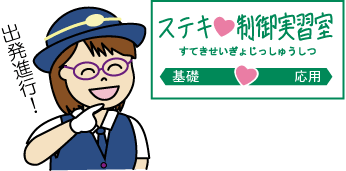 |
|
|||
| みなさんこんにちは。見習い講師の里枝です。今回は、鉄道模型の信号機のいよいよ本格的にしちゃいます。 単純な閉塞区間での信号動作+タイマー復帰という前回の仕様で回路もそのままにPCBEを使ってパターンを起こし、例によって「趣味の基板屋さん」にて専用基板の製作をお願いしました。 さらなる小型化と汎用化に成功しましたので、鉄道模型で自動信号制御を検討されている方々にもお試し頂ける内容だと思います。 |
||||
| 本機の仕様について |
| 赤・黄・青(緑)の三灯式とします。線路上もしくは線路横にリードスイッチやフォトリフレクタなどで、車両を感知し、信号を制御します。尚且つ、車両の進行状況に応じて手前の信号機を赤⇒黄、黄⇒青へと連動で制御をかけます。さらに、これらの動作はレイアウトの状況に応じて、タイマーによる自動的な信号制御も可能な仕様にします。 |
| 本機の動作について |
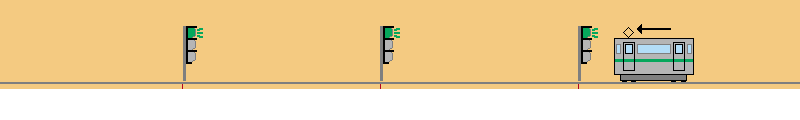
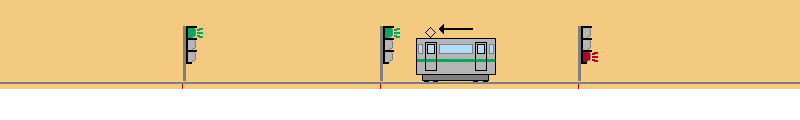
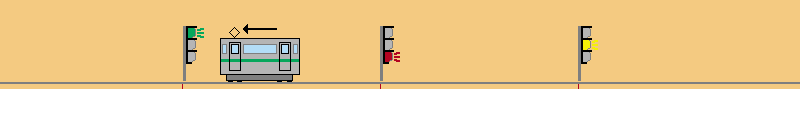
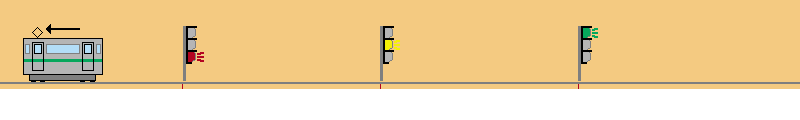
| その先の信号がない場合、中央または左の信号がいつ青になるかという疑問をもたれた方は、後述の解説をご覧ください。 |
| 外部インターフェースの設計 |
| 上の絵から分ることは、線路に検知スイッチを用意して列車が通過した時に自己保持をONにさせ、先の区間に達したら自己保持回路をOFFさせればよいという単純な考えが浮かびます。この定義だけならとっても簡単そうですね。一応、今回は閉塞区間ごとにユニットを製作して、独立制御させることを前提に進めます。 |
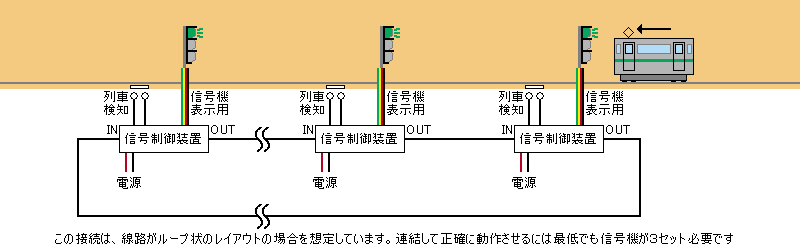
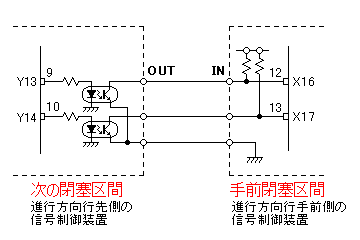
| 制御装置同士をつなげる部分は上の図のようになっています。Y13とY14につながっているフォトカプラを介して手前の閉塞区間に対し赤→黄や黄→青の制御を渡しています。Y13(Y14)がONになるとフォトカプラ内のLEDが光り、その光で同じく内臓のフォトトランジスタがONになってX16(X17)がLowレベルになることにより、入力信号がPICに伝わります。(連枝の入力はLowレベルでONです) |
| シーケンス回路の設計 |
| 前述の動作解説の中で、左または中央の信号機がいつ青になるかということですが、一番右信号機のOUT端子を一番左の信号機のIN端子に接続するか、それを接続せずに一番左(先)の信号機をタイマー時間設定で自動的に復帰するようにすれば、それより先の信号機から情報をもらわなくても解決できます。鉄道模型に使う場合に規模によっては、1〜2台での運用も考えられるのでこの機能は便利だと思います。また、レイアウトが変わるたびにタイマーの設定値をプログラミングで変更するのが難しいので、簡単に1〜15秒の間で1秒単位で設定できるように工夫しています。+αの機能を付けたら、複雑な回路になってしまいましたが、詳しくはシーケンス回路をじっくり見てください。但し、じっくり見なくても、シーケンス回路を解読できなくても、ちゃんと製作すれば実感できると思います。 |
| 信号機(番外編) 「鉄道模型用信号機を本格的にするの巻」回路図 |
| 毎度お馴染みPIC 16F84A周辺回路です 専用基板に合わせて、LEDの電流制限抵抗をそれぞれに独立させました 2012.10.09 列車確認は通過型センサーやマイクロスイッチなど、各自で工夫してください。ただ単に動作テストするだけでしたら、押している間だけONになるスイッチなら何でもOKです。 フォトリフレクタを列車検知に使う場合、物によってはプルアップ抵抗が10kΩでは小さすぎるかもしれません。 「電子おみくじ」でも解説していますが、47kΩ位になるでしょうか、ここはトライしながら抵抗値を決めてください。 フォトカプラ用のLEDは470ΩでもOKです |
| 補足事項 |
| **タイマー設定について ご注意** 連結モード(他の信号機からの情報で動作)/タイマーモード(タイマーで自動復帰)の設定切替およびタイマーの時間設定は、電源ON時またはリセット時にスイッチの状態を読み込んでセットされますので、電源が入っている状態で変えても変更になりません。 タイマー設定BCDスイッチの値が0(ゼロ)の場合は連結モード(タイマーは無効)となります。また、タイマーモード時の設定時間は、赤から黄になるまでの時間と、黄から青になるまでの時間は同じ秒数でしか設定できませんのでご了承ください。 BCDスイッチの時間設定 BCDスイッチの時間セットは、X01=1秒・X02=2秒・X03=4秒・X04=8秒の設定となっています。もし時間設定を3秒にしたい場合はX01とX02をONにすれば(1秒+2秒という計算で)3秒の遅延設定となります。ここはご希望の時間に合わせてスイッチの設定を変更してください。 |
| プリント基板のお求めはこちら |
「趣味の基板屋さん」で販売しています。ご希望の方は、「趣味の基板屋さん」のサイトで直接お申し込みください。
この専用基板を使用した組み立てマニュアルはここからダウンロードできます。 |
| パーツリストはこちら |
※今回は例題として1kΩの抵抗を使用していますが、この電流制限抵抗は使用するLEDによって変わりますので、定格の範囲内で明るさを見ながらの現物合わせが最良だと思います。その場合、ピンソケットや丸ピンICソケット(シングル)および通常のICソケット(8P:一部のピンは抜いておく等で使わないようにして)を基板にハンダ付けしておいて、抵抗を任意の値で差し込んで使用するという方法もあります。 |
| シーケンス回路はこちら |
| 完成写真はこちら |
前回制作した時の写真です
|
|||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
| メニューへ戻る |