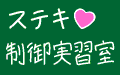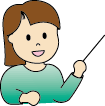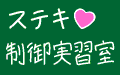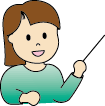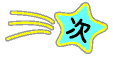| 1 |
外部の信号(電源)を、ON/OFFできる |
中の接点を動かすだけの小さな電流で、大きな電流を制御できる。例えば、車のホーンやライトなどはリレーを介して動作させています。 |
| 2 |
ON/OFFを反転できる |
電流が流れたら接点をOFFにする動作。B接点を使うことによって、ON/OFFの動作を反転することができます。 |
| 3 |
一度に何回路かをON/OFFできる |
リレーの中には1・2・4回路内蔵のものがある。1つの信号で同時に何回路かをON/OFFできます。さらにリレーを並列につなげて、それ以上にすることも可能です。 |
| 4 |
自己保持で、ON状態を維持できる |
これが結構重要だとおもいます。後でじっくりと解説していきます。 |