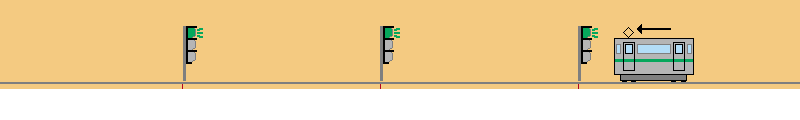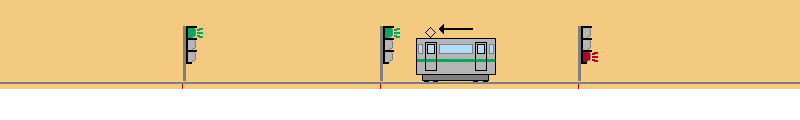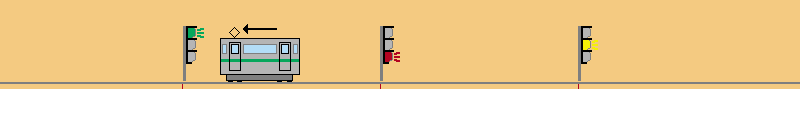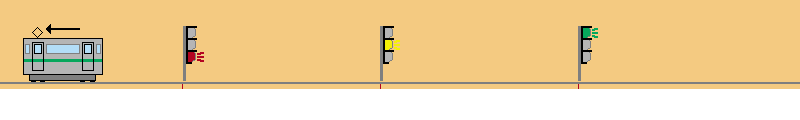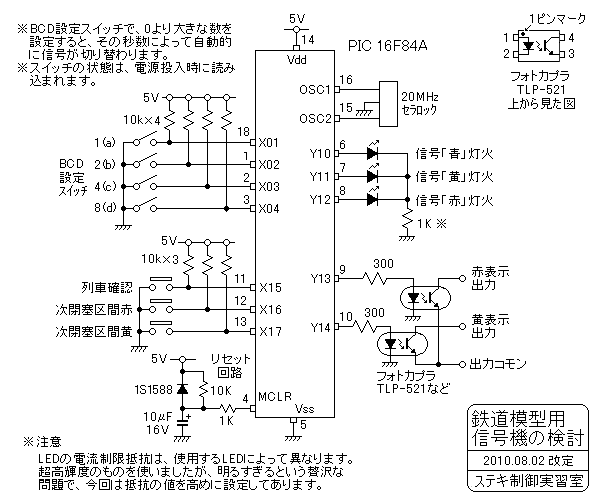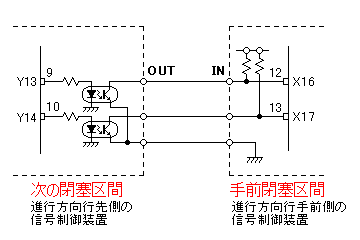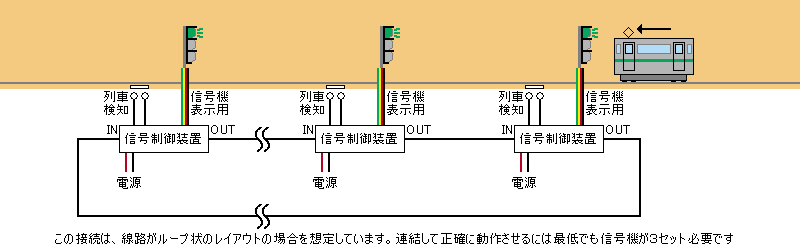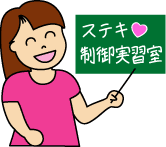
|
信号機(番外)鉄道模型の信号を検討するの巻 |
| 実践課題メニューへ戻る |
| メインメニューへ戻る |
調べてみると、本物の鉄道は信号で区切られた閉塞区間(へいそく くかん)という単位で制御していて、1つの閉塞区間には車両が1編成しか入らないという前提で、信号制御しているそうです。詳しく知りたい人は自分で調べてください。今回の実習では閉塞区間の信号制御と、簡易的なタイマーで模型に使える信号制御の2通りに対応した信号機をつくってみます。ちなみに私は鉄道模型を持っている訳じゃないので、作った信号機を眺めるだけです。
信号機をシーケンス制御する検討ですから、ポイントや列車の速度制御については全く考えません、さらっといきましょー。